ブディスト・メディテーションの今(2) アメリカに根づいた三つの実践──禅・ヴィパッサナー・チベット仏教の現在地
Jul 10, 2025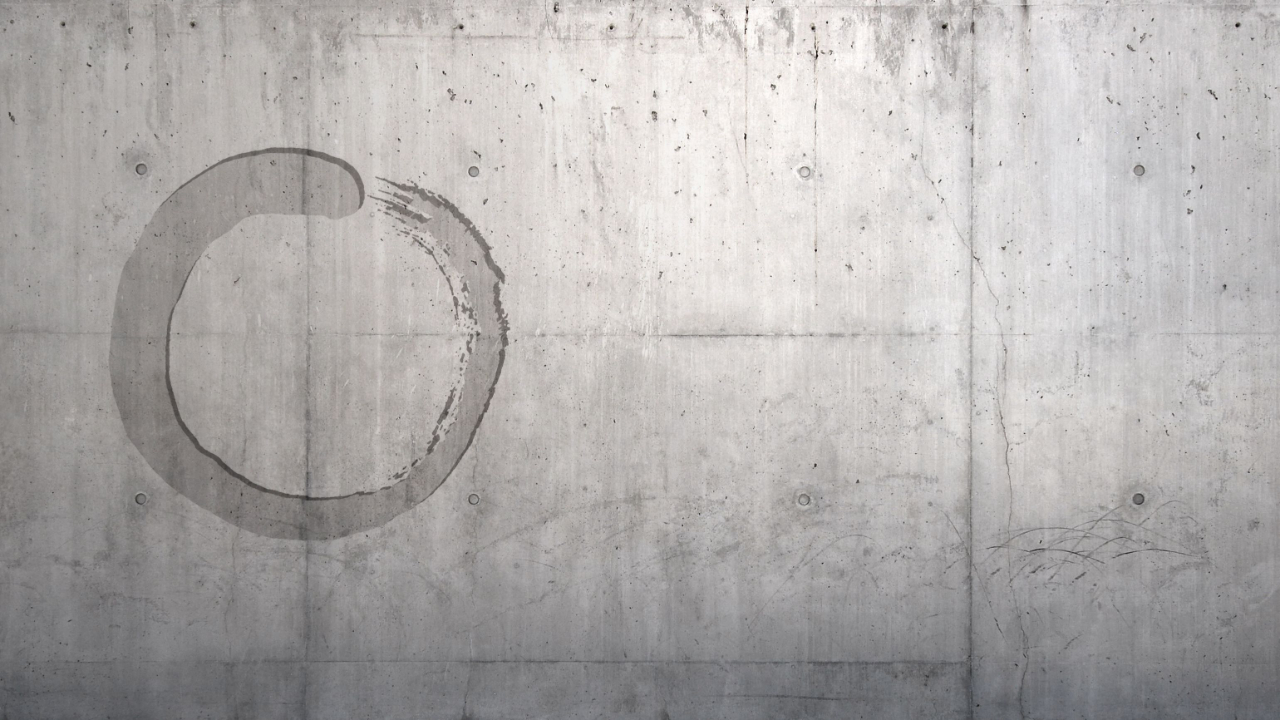
Part 2 アメリカに根を下ろした三つの瞑想──禅・ヴィパッサナー・チベット仏教の現在地
前回(Part 1)では、アメリカの瞑想市場がいかに急成長しているか、そしてその中核にあるのが「ブディスト・メディテーション」という実践であることをご紹介しました。
今回はそこから一歩進んで、アメリカ社会に深く根づいてきた三つの実践──禅・ヴィパッサナー・チベット仏教──が、それぞれどのように紹介され、定着してきたのかを掘り下げてみたいと思います。
宗派や伝統というよりも、生き方や実践文化として受け入れられてきたこれらの瞑想が、現代社会にどのようなかたちで活用されているのか。その歩みと広がりに焦点をあてて、全体像を整理していきます。
禅──沈黙と坐禅が導いた実践文化の定着
禅は、20世紀前半に仏教学者・鈴木大拙(D.T. Suzuki)によってアメリカに紹介されました。彼の著作は、アラン・ワッツやジョン・ケージといった思想家・芸術家にも影響を与え、東洋思想としての禅が広まりました。
そして1960年代、曹洞宗の僧侶・鈴木俊隆(Shunryu Suzuki)がアメリカに渡り、サンフランシスコ禅センターを創設したことで、禅は「坐る実践」として根づきはじめます。『禅マインド・ビギナーズマインド』は、アメリカで今も読まれ続けている禅の入門書の一つです。
今日では、全米各地に禅センターが存在し、大学や医療機関とも連携しながら、坐禅を中心としたリトリートや教育活動が続けられています。
ヴィパッサナー──心理療法や教育現場に根づいた観察の実践
ヴィパッサナー瞑想は、テラヴァーダ仏教に基づく実践として1970年代以降に広まりました。アジアで修行したジャック・コーンフィールド、ジョセフ・ゴールドスタイン、シャロン・サルツバーグらがその代表的存在です。
彼らが設立した Insight Meditation Society(IMS)や Spirit Rock Meditation Center では、呼吸や身体感覚への気づきを中心としたリトリートが行われ、数万人規模の実践者を育成してきました。
とくに臨床心理や教育分野との連携が深く、心理療法士・医療従事者・教師向けのプログラムが整備されており、アメリカのマインドフルネス実践の一大基盤を築いています。
チベット仏教──文化的信頼と現代的応用を備えた精神文化の展開
チベット仏教は、アメリカにおいては比較的後発の実践体系として導入されましたが、ダライ・ラマ法王の活動によってその慈悲と非暴力の哲学が広まり、文化的な信頼を集めてきました。
1970年代以降、カギュ派・ニンマ派・ゲルク派などの系譜に連なる複数のラマたちが、全米各地にリトリートセンターや教育機関を設立し、それぞれの伝統に基づいた瞑想指導を広めてきました。Garchen Institute(アリゾナ)や Kunzang Palyul Choling(メリーランド)、Karma Triyana Dharmachakra(ニューヨーク)などがその代表例です。
こうした多様な展開がある中で、チョギャム・トゥルンパ・リンポチェの活動は特筆すべき事例です。1970年代から、Shambhala Centers や Naropa University の設立を通じて、瞑想・教育・芸術・心理療法を結びつける新しい文化基盤を生み出しました。
とくにナローパ大学では、瞑想と心理学・精神医療を統合する教育プログラムが展開され、Contemplative Psychotherapy(内省的心理療法)という分野を先駆的に確立しています。
それぞれが社会のなかで根づいた背景
これら三つのブディスト・メディテーションは、いずれもアメリカ社会に深く根づき、実践者の個人生活にとどまらず、教育・医療・心理・芸術といった制度的な領域にまで広がりを見せてきました。
- 禅は、坐禅と沈黙を軸とした実践文化として、ビジネス研修、大学講義、精神医療の補助療法、そしてアート教育などに「静けさ」や「間」の感性をもたらしました。
- ヴィパッサナーは、気づきと観察を基盤に、心理療法・メンタルヘルス・教育現場での実践として発展しています。Insight Meditation SocietyやSpirit Rockでは、医療者やカウンセラー向けのプログラムも整備されています。
- チベット仏教は、多様なラマによって全米に拠点が築かれるなか、特にトゥルンパの現代的展開では、空性・慈悲・ボーディチッタといった視点が現代語で翻訳され、芸術・教育・心理療法と融合する独自の教育モデルが提示されました。
こうした三つの道はいずれも、アメリカ社会においてブディスト・メディテーションを「文化的インフラ」として定着させる大きな基盤となってきました。
次回(Part 3)では、これらの伝統がアメリカ社会の中でいかに“信頼”と“人気”を獲得してきたのか──制度、センター、著名人の支援、文化的影響などを詳しく見ていきます。

