ブディスト・メディテーションの今(4) いま世界で信頼されている瞑想指導者たちー現代アメリカに根づいた“実践者の顔”
Jul 10, 2025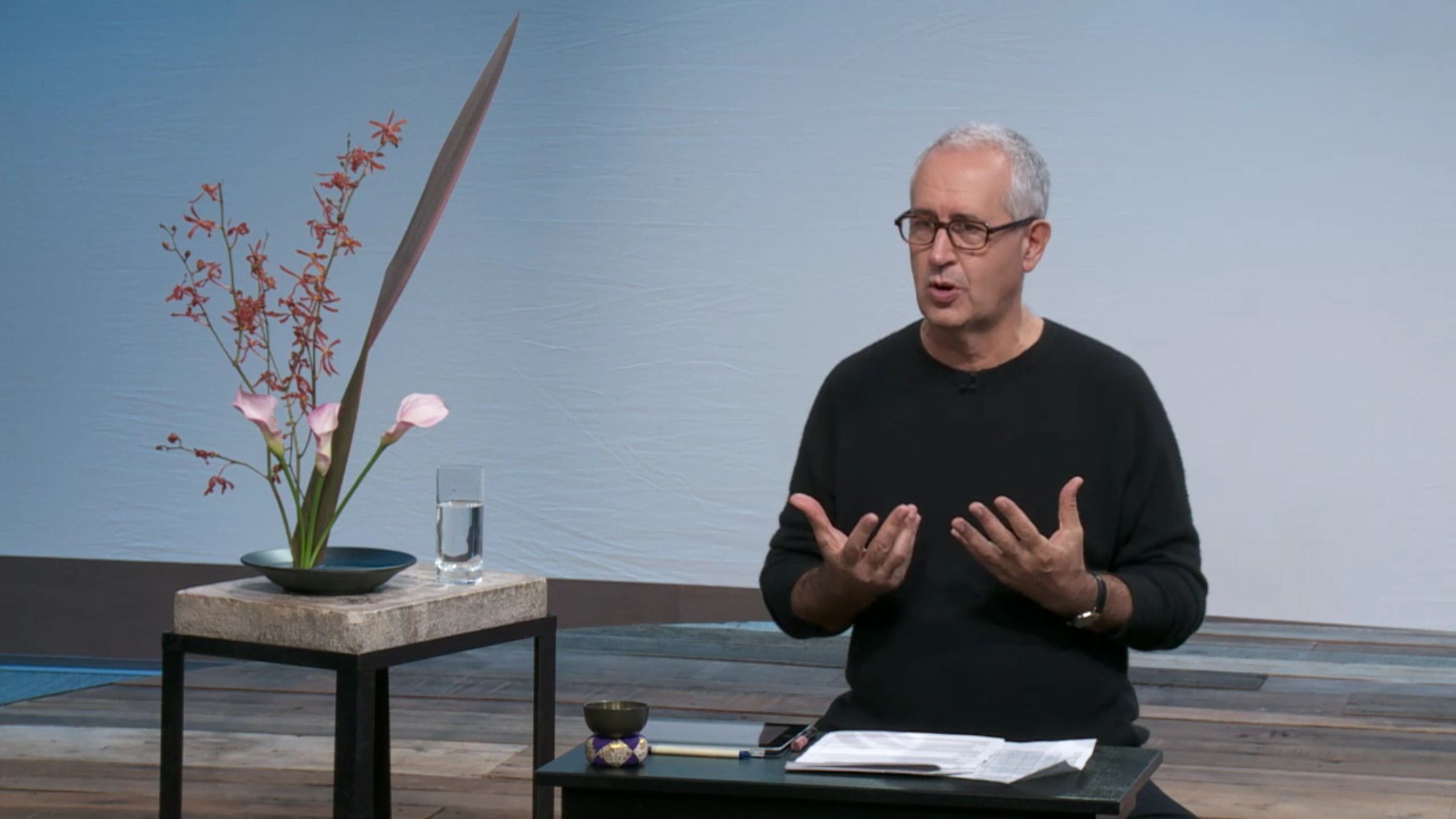
アメリカではブディスト・メディテーションが、医療・教育・心理・文化といった分野を横断しながら、深く社会に根づいています。前回までは、その制度的基盤や市場データをもとに、「なぜブディスト・メディテーションが信頼されたのか?」という構造的な問いを掘り下げてきました。
今回は少し視点を変えて、実際に現代のアメリカで活躍している実践者たちの姿を通じて、ブディスト・メディテーションがどのように人々の暮らしと結びついているのか、そのリアルな広がりを感じていただきたいと思います。
書籍が世界的ベストセラーとなった人、年間1万人を超える生徒にリトリートを提供する人、死の臨床ケアに瞑想を導入している人、科学と仏教を架橋している僧侶──その多様さは、従来の“メディテーション・ティーチャー”という枠を超え、実社会の多様な領域と接続された、新しい実践者像を形づくっています。
Part 4 アメリカで活躍するブディスト・メディテーション・ティーチャーたち
ここでは、いま、誰が、どのように、ブディスト・メディテーションを世界に届けているのか。その一端をご紹介していきます。
【ヴィパッサナー系】
ジョセフ・ゴールドスタイン(Joseph Goldstein)
Insight Meditation Societyの共同創設者。年間1万人以上が参加するリトリートを主催し、アメリカにおけるヴィパッサナー実践の基盤を築いた最重要人物の一人。多くの瞑想指導者の師でもある。New York Times Magazine(2020年4月14日号)にて、パンデミック下における信頼される瞑想指導者として特集された。
シャロン・サルツバーグ(Sharon Salzberg)
メッタ(慈しみ)の瞑想を広めた教育者。代表作『Real Happiness』は20万部以上を売り上げ、女性実践者として幅広く支持されている。『Real Happiness』はNew York Timesベストセラーリスト入り。NPRやTime誌など多数メディアでも紹介された。
ジャック・コーンフィールド(Jack Kornfield)
Spirit Rock Meditation Centerの創設者。年間2万人以上が参加するリトリートを開催し、臨床心理学と仏教実践を融合させた教育スタイルで知られる。New York Times Magazineで「アメリカにおける真のマインドフルネス・パイオニア」として紹介されている。
オーウェン・ブローダー(Owen Broder)
若手世代に向けた都市型ヴィパッサナー実践の担い手。ライフスタイルとしての瞑想を提唱し、内省と社会生活の統合を図る。
ノア・レヴィン(Noah Levine)
パンクロック文化出身の回復支援指導者。Against the StreamやDharma Punxを通じて、若年層へのアプローチを開拓。著書『Dharma Punx』は20万部超のベストセラー。
【禅系】
ノーマン・フィッシャー(Norman Fischer)
サンフランシスコ禅センターの元指導者であり、詩人でもある。Googleや医療機関との協働を通じて、禅と倫理・芸術・教育の接点を築いている。New York Times紙にて音楽家としても“inspiring”と評され、Lion’s Roar誌でも特集されるなど幅広い文化的評価を受けている。
スティーブン・バチェラー(Stephen Batchelor)
“世俗仏教(Secular Buddhism)”を提唱し、信仰に依存しない合理主義的な仏教実践を展開。著作や講演を通じて国際的な議論を牽引している。Vanity Fair誌によって「Secular Ageにおける仏教の再考者」として特集された。
ジョアン・ハリファックス(Joan Halifax)
禅僧としての修行とともに、ホスピスや医療の臨床現場にマインドフルネスを導入。ケアと仏教の融合という分野を切り開いている。On Being Projectにて「死を看取る助産師(a midwife to the dying)」として広く紹介され、Wired主催のWisdom 2.0にも登壇。
ジェーン・マクガニガル(Jane McGonigal)
女性性と禅的瞑想を融合させたプログラム開発者。身体性と創造性に根ざした新しい実践文化を構築しており、アートやフェミニズムとの接点も注目されている。Time誌にて「ビデオゲームが健康を改善する理由」として瞑想との接続について論じた記事が掲載されている。
【チベット仏教系】
ペマ・チョドロン(Pema Chödrön)
チベット仏教ニンマ派の比丘尼。代表作『When Things Fall Apart』は世界的ベストセラーとなり、多くの読者に慈悲と勇気の実践を届けている。New York Magazine(The Cut)にて「人生の激動期に読むべき本」として同書が特集された。
ミンギュール・リンポチェ(Yongey Mingyur Rinpoche)
脳科学と瞑想をつなぐ国際派僧侶。YouTubeでの講話は累計数千万回を超え、科学と仏教の橋渡しとして世界的な影響力を持つ。著書『The Joy of Living』がNew York Timesベストセラー入り。National Geographicでもその脳波研究が紹介された。
スーザン・パイバー(Susan Piver)
チベット仏教実践者として「Open Heart Project」を主宰。2万人を超える会員とともに、日常生活に根ざした実践をオンラインで展開する先駆者。
セラ・ワイダー(Sara R. W. Wider)
ニンマ派のラマであり、女性僧院文化の再建に取り組む実践者。現代における“神聖な日常”を再解釈する活動を行っている。
ロバート・サーマン(Robert Thurman)
コロンビア大学仏教学名誉教授であり、アメリカにおけるチベット仏教研究の草分け的存在。1987年にはダライ・ラマとともに「Tibet House US」を設立し、文化保存・教育・瞑想実践の拠点を築いた。彼の著作『The Tibetan Book of the Dead(英訳)』『Inner Revolution』は西洋における仏教的精神改革の指南書とされ、Time誌によって「世界で最も影響力のある精神的リーダー25人」の一人に選出されたこともある。
【科学・制度的導入】
ジョン・カバット=ジン(Jon Kabat‑Zinn)
医療分野に瞑想を持ち込んだMBSRの創始者。大学病院において、ストレス・慢性痛・がん治療に活用される瞑想プログラムを開発し、非宗教的かつ科学的アプローチとして普及させた。New York Times、Scientific American、The New Yorkerで繰り返し特集され、非宗教型仏教瞑想の構造的普及を牽引した人物と評価された 。
リック・ハンソン(Rick Hanson)
心理学者・神経科学者。『Buddha’s Brain』『Hardwiring Happiness』などを著し、New York Timesベストセラーにランクイン。NASAやGoogle、オックスフォードで講演し、CBSやNPR、BBCでも取り上げられるなど、仏教的神経可塑性研究の先端を担う。
【芸術・医療との架橋】
レベッカ・ペトラス(Rebecca Petress)
ヴィジュアルアートとマインドフルネスを融合させた教育者。美術学校やギャラリーでのワークショップを通じて、創造性と内省を結びつけている。
ラッセル・ポール(Russell Paul)
チベット仏教の世界観を取り入れたホリスティック・ヘルス指導者。音響療法と瞑想を統合し、医療現場における癒しの可能性を追求する。
タラ・ブラック(Tara Brach)
仏教心理学とコンパッション瞑想の実践者。彼女のポッドキャストは累計5,000万回以上再生され、アメリカ全土に幅広い支持を持つ。
※Psychology Todayで“コンパッション・メディテーションの第一人者”と紹介され、New York Timesのカルチャー欄にも登場している。
ダイアナ・ウィンストン(Diana Winston)
UCLA Mindful Awareness Centerのディレクター。年間数千名に指導を行い、科学とマインドフルネスの接続に貢献している。
※Scientific AmericanおよびUCLA Newsroomで、科学的根拠に基づくマインドフルネス普及活動が紹介されている。
アンジェラ・センツ(Angela Senz)
ヴィパッサナー瞑想を基盤に、BIPOCやLGBTQ+のための包括的な実践コミュニティを牽引。多様性と仏教実践の融合という新たな文化的展開を示している。
【仏教的実践の源流】
チョギャム・トゥルンパ(Chögyam Trungpa)
チベット仏教カギュ派の転生活仏。西洋初の本格的瞑想センター創設者であり、ナローパ大学を開設。Shambhala Trainingなど、仏教と芸術・教育・心理を融合させた実践モデルを構築し、1970年代以降のアメリカ瞑想文化の礎を築いた。彼は米国ラジオ、雑誌、テレビなど多数のメディアで一般層に発信し、仏教ダルマを“文化的文脈に移す”働きを担った 。
ティク・ナット・ハン(Thich Nhat Hanh)
ベトナム禅僧で、「Engaged Buddhism(実践的仏教)」を体系化。呼吸・歩行・食事を含む日常すべてをマインドフルネスの場と位置づけ、アメリカの教育・医療・環境運動に多大な影響を与えた。TimeやNYP、The Guardianなどで紹介され、すでに“マインドフルネス普及の始祖”として位置づけられている他、ニューヨーク市が彼に通り名を付与したことも報道された 。
鈴木俊隆(Shunryu Suzuki)
日本の曹洞宗僧侶で、1959年にサンフランシスコ禅センター(SFZC)を設立。アメリカにおける禅の本格的な普及を担い、宗派を超えて多くの実践者を育てた。著書『Zen Mind, Beginner’s Mind』は1970年代以降のアメリカ瞑想文化に大きな影響を与え、今なお禅とマインドフルネスの入門書として読み継がれている。New York Times、Lion’s Roar、Tricycleなどの主要仏教メディアでも繰り返し特集され、その思想は欧米の瞑想文化の源流として位置づけられている。
瞑想実践は“社会”の中へと広がっている
こうして見てくると、現代のブディスト・メディテーションは、もはや「修行者たちの静かな営み」ではありません。芸術、教育、心理、社会運動、ビジネス、医療、テクノロジー──あらゆる領域に触れながら、それぞれの文脈で“いまを生きる”実践として展開されています。そしてこうした実践の流れは、アメリカという特殊な土壌に留まるものではありません。文化や言語を越え、私たちの暮らしに活かせるヒントと可能性を秘めています。
次回のPart 5では、「なぜ“いま日本で”ブディスト・メディテーションが必要なのか」という問いに立ち返り、その背景と教育体系をご紹介していきます。

